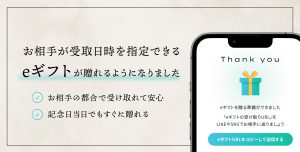年末は何かと慌ただしく、 おせち料理を一から手作りするのは難しい…そう感じる方も多いのではないでしょうか。それでも、日本の伝統料理「おせち」に込められた意味や由来を知ることで、 家族との会話がより豊かになり、年のはじまりに彩りが添えられるはずです。
本記事では、おせち料理の歴史~いまどきのおせち、重箱に込められた願いについて、 わかりやすくご紹介します。
江戸〜昭和に見る「おせち料理」のうつりかわり
江戸時代:庶民の祝い膳として定着
江戸時代に入ると、それまで宮中の儀式として供されていたおせち料理が、庶民の暮らしにも広がりを見せはじめます。 この頃には「祝い肴三種」(黒豆・数の子・田作り)が定番となり、保存性に優れた料理を重箱に美しく詰めるスタイルが定着しました。
年のはじまりに、願いを込めて料理を重ねる—— おせちは「食べる」だけでなく、「飾る」文化として、家庭の中にそっと根づいていった時代でもあります。
昭和時代:台所から百貨店へ——おせちの新しい風景
戦後になると、「おせち」という言葉が一般に浸透し、昭和30年代には百貨店やスーパーで市販のおせちが並ぶようになります。 冷蔵庫の普及や家族構成の変化にともない、手づくりから購入へと、おせちのスタイルも徐々に移り変わっていきました。
昭和の後期には、和洋折衷のメニューや、子ども向けの甘めの味付けなど、バリエーションも豊かになりました。 それでも、黒豆や数の子といった定番の品々は変わらず重箱に並び続け、「変化するもの」と「変わらないもの」が共存していきます。時代が移ろっても、重箱に込められた願いや家族のつながりは、受け継がれていきます。
令和時代:広がる選択肢、自由なおせちのかたち

令和の時代を迎え、おせち料理はより多様で自由なスタイルへと進化しています。 伝統的な和の要素を大切にしつつ、洋風オードブルや中華料理を取り入れた“和洋折衷おせち”が主流となり、ローストビーフやパテなど、華やかな料理が重箱を彩るようになりました。
また、重箱にこだわらないプレート盛りや、好みの品を自由に選べる“カジュアルおせち”も登場し、暮らしに寄り添った柔軟なスタイルが注目を集めています。 少人数世帯の増加にともない、1〜2人前のコンパクトなおせちや、好きな料理だけを詰めた“マイおせち”も人気に。 近年では、スイーツを中心に構成された“甘味おせち”など、嗜好性の高い商品も登場しています。
予約は例年、8月〜9月に始まり、11月に入ると販売のピークを迎えます。 人気商品は11月末には完売することも多く、早めの早めの予約が定番に。そして、注目されているのが、料亭監修の三段重や、肉料理・海鮮料理を中心に構成された豪華なセットです。 ローストビーフやいくらなど、贅沢な味わいが年のはじまりを華やかに演出します。
また近年では、キャラクターとのコラボレーションや、SNS映えを意識した盛り付けなど、Z世代やファミリー層に向けた“推しおせち”も登場しており、 おせちは今、伝統を受け継ぎながら、自分らしく楽しむ時代へと歩みを進めています。
大五グルメセレクションで選べるおせちのご紹介
大五グルメセレクションでは、魅力あふれるおせち料理を多数ご用意しております。 それぞれに異なる個性があり、人数やお好みに合わせてお選びいただけるのも嬉しいポイントです。 今回は、特長とともに3種類のおせちをご紹介いたします。
選び抜かれた味わいを重箱に詰めて、冷凍便にて2025年12月30日お届け予定。 予定数に達し次第、受付終了となりますので、ご予約はどうぞお早めに。
好評につき販売予定数に達しましたので、
「おせち2026」の予約受付を終了いたしました。

「葵(あおい)」三段重
| 監修:祇おん江口 | 通常価格17,280円(税込) |
- 3人前・42品目を詰め合わせた、バランスの良い三段重
- 黒豆や数の子などの定番に加え、ローストビーフなど洋風メニューもラインアップ
- 家族で囲む食卓にちょうどいいサイズ感
- 冷凍便/風呂敷包み・化粧箱入りの特別仕様
予約受付終了

「春望(しゅんぼう)」三段重
| 監修:日本橋OIKAWA | 通常価格12,960円(税込) |
- 2人前・38品目を詰め込んだ、上品でコンパクトな三段重
- 京風のやさしい味わいに、洋のエッセンスを添えた繊細な仕立て
- 少人数で迎える穏やかな新年や、ご夫婦でのひとときにぴったり
- 冷凍便/風呂敷包み・化粧箱入りの特別仕様
予約受付終了

「慶雲(けいうん)」与段重
| 監修:祇おん江口 | 通常価格30,240円(税込) |
- 4人前・6.5寸・65品目を詰め込んだ、豪華な四段重
- 和と洋が織りなす華やかな構成で、見た目にも味わいにも満足感を
- ご家族やご親戚との集まりにふさわしい、たっぷりのボリューム
- 冷凍便/風呂敷包み・化粧箱入りの特別仕様
予約受付終了
おせちは、かつての「伝統を守る料理」から、「自分らしく選んで楽しむ体験」へと姿を変えてきました。 それでも、黒豆に込められた“まめに暮らせますように”という願いや、数の子に託された“子孫繁栄”の祈りは、今も変わらず重箱の中に息づいています。
新しい年のはじまりに、ご家族や大切な方と囲むにふさわしい一品を、どうぞお選びください。
時間が経っても、美味しさそのまま。ひと工夫で、食卓に新しい彩りを。

翌日のおせちも“ごちそう”に見せる盛り付けのコツ

黒や朱の器が、料理に静かな華を添える
残りものも、そのままでは“昨日の続き”になりがち。 黒や赤の器に移すだけで、ぐっと引き締まり、 少量でも凛とした存在感に。 特に黒皿は、食材の色を美しく引き立ててくれます。
余白」を意識して、間をととのえる
少し余白を残して、3〜4品をゆったりと並べるだけで、 それぞれの料理が主役のように輝きます。 残りものも、まるで“選ばれたおつまみ”のような佇まいに。


“向き”と“高さ”で立体感を出す
海老など立体的な食材は奥に、平らなものは手前に。 形の違いが織りなす配置が、自然なリズムを生み出します。 盛り付けの順を少し変えるだけで、印象がぐっと引き締まります。
小物をひとつ添えて、お正月の名残を
水引や松葉、南天の実をそっと添えるだけで、 “まだお正月を楽しんでいる”空気が漂います。 使い回しの飾りでも、残りものの印象をふわりと消してくれます。


味はそのまま、組み合わせで新しい一皿に
黒豆+クリームチーズ、栗きんとん+バターでスイーツ風に。 味を変えなくても、組み合わせを少し変えるだけで、 いつもの一品が新鮮に映ります。
お正月の一日目に残ったおせちも、二日目にはひと工夫で新たな魅力を。 小皿に丁寧に盛り付ければ、まるで小さな宝石箱のよう。 味わいはそのままに、見た目にひと手間添えるだけで、食卓の雰囲気がぐっと華やぎます。 家族の会話にも、自然と笑顔が咲くひとときに。写真は「葵(あおい)」三段重を使った盛り付け例です。
ご家族や大切な方と迎えるお正月にふさわしい逸品を、ぜひお選びください。